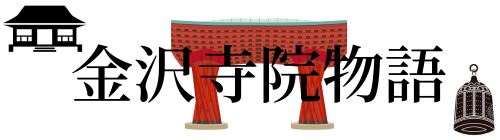KOUSAIJI TEMPLE
500年の歴史を持つ真宗大谷派の広済寺。武佐の御忌では尾山御坊ゆかりの宝物を開帳します。
金沢の歴史と徳川の縁を紡ぐ、静寂なる武佐山
広済寺は、金沢市の中心部に位置する真宗大谷派の仏教寺院です。文亀元年(1501年)に祐乗坊によって創建されて以来、加賀百万石の歴史と文化を静かに見守り続けてきました。金沢城の礎となった「尾山御坊」との深いつながり、そして徳川家康公から拝領した「葵の御紋」を寺紋とするなど、当寺院は激動の時代を生き抜き、数々の物語を今に伝えています。境内は、歴史を物語る静謐な空間が広がり、訪れる人々に心の安らぎと深い感動を与えています。金沢の奥深い魅力を、広済寺で感じてみませんか。
広済寺の歴史と由緒
広済寺は、文亀元年(1501年)に実如上人の弟子である祐乗坊が加賀に下向して創建した真宗大谷派の仏教寺院です。当初は、現在の金沢城二の丸跡地にあった御山御坊(現在の石川門外、百間堀上に御坊遺跡「お茶所ヶ井」が残る)の看坊(御坊を統轄する役職)として滞在し、寺としての体裁を整えていきました。金沢廣濟寺はこの祐乗坊を初代開祖としています。
その後、「石山合戦」の最中、織田信長は柴田勝家を加賀に攻めさせ、天正8年(1580年)3月にはついに御山御坊が陥落しました。御山御坊を退去した三代看坊・祐盛と四代・祐玄は、内川郷や安江郷の山中に小庵を営み、山川・別所・小原・平栗・新保等の門徒と共に、困難な時代にあって本願寺の法灯を守り続けました。
そして、寛永13年(1635年)に現在地を賜り、今日に至ります。この時以来およそ400年、毎年3月の初めには、蓮如上人・実如上人両上人の追弔法要である「武佐の御忌」を営み、寺に伝わる宝物が開帳されます。
当寺院の山号である「武佐山(むさざん)」は、本家である滋賀県近江八幡の江州武佐広済寺の山号に由来し、金沢広済寺も「ムサ寺」の愛称で親しまれています。
雨を呼ぶ侍女「おちよぼ」:武佐の御忌に秘められた伝承
広済寺に伝わる「武佐の御忌」には、心温まる、そして神秘的な伝承があります。その昔、当寺に仕えていた侍女「おちよぼ」は、朝夕欠かさず仏様にお供えする水を汲んでおりました。その「おちよぼ」が、「武佐の御忌」の際には、雲を呼び雨を降らす蛇体となって参詣にくるため、昔から「武佐の御忌には必ず天気が荒れる」と伝えられています。石川門の外、百間堀上にある御坊遺跡「お茶所ヶ井」は、おちよぼが水を汲んでいた井戸の跡とされています。この伝承は、当寺と地域の人々との深い結びつき、そして信仰の厚さを今に伝える物語です。
寺の歴史を紐解く「梵鐘」の物語
広済寺には、その歴史の深さを物語る印象的なエピソードが伝わっています。 ある時、各地の寺院の鐘を撞くことを趣味とする一人の粋人が広済寺を訪れ、鐘を撞きました。ところがその音は鈍く響き、調べたところ鐘の底にひび割れが見つかりました。そのため、住職は止む無く鐘を高岡の銅器会社に処分のため売却することにしました。
しかし、住職は以前からこの鐘に刻まれていた漢文の内容が気になっていました。そこで、処分寸前の鐘をすんでのところで引き戻し、郷土史家の中田隆二氏にその漢文の調査を依頼したのです。
中田氏による解読の結果、この鐘には驚くべき内容が記されていることが判明しました。それは、かつて加賀一向一揆の拠点であり、現在の金沢城の場所に位置していた「尾山御坊」の由来に関する記述でした。
刻まれた漢文によると、文亀元年(1501年)に江州広済寺十代・厳誓坊祐念の次男である「祐乗坊」が、本願寺の実如上人の命を受け、尾山御坊に長く滞在し、寺院を建立して布教活動を行ったと記されていました。この祐乗坊こそが、まさに金沢広済寺の初代開祖だったのです。
この梵鐘の発見は、金沢広済寺が尾山御坊、そして本願寺との密接なつながりの中で誕生し、金沢の歴史と共に歩んできた証を改めて明確にするものでした。
葵の御紋が語る徳川家との深いつながり
広済寺の歴史を語る上で欠かせないのが、徳川家との特別な縁、そして寺紋として受け継がれる「三つ葉葵」の御紋です。
滋賀県近江八幡に位置する本家広済寺の八代住職・岡崎安休(あんきゅう)は、戦国武将・浅井長政の異母兄弟にあたる人物でした。僧侶となった安休は優れた知恵と軍略の才を持ち、天正年間には顕如の命を受け、加賀・越前の門徒衆を率いて織田信長打倒のための指揮を執るなど、激動の時代を生きました。
この安休には「感」と「武佐」という二人の娘がいました。彼女たちは揃って、徳川御三家の一つ、水戸藩初代藩主・徳川頼房公の乳母として仕えました。中でも武佐は、頼房公とその側室の長男である松平頼重公(高松藩初代藩主)と、次男である徳川光圀公(水戸藩二代藩主、水戸黄門として知られる)の養い親という重責を担い、彼らの命を守り育てたのです。
安休は、娘・武佐が嫁いだ三木家と水戸徳川家を通じ、徳川家康公と親交を深めました。この由縁により、家康公より家紋である「三つ葉葵」の御紋と刀を拝領したと伝わります。このことから、本家広済寺では葵の紋を用いるようになり、後には重要な儀式で松平頼重公より拝領した葵御紋の幕を使用したとも伝えられています。
このようにして安休が家康公より授かった葵の御紋は、遠く金沢の広済寺にも受け継がれ、今日まで寺紋として大切に用いられているのです。広済寺の随所に息づく葵の御紋は、激動の時代に紡がれた歴史と、徳川家との深いつながりを今に伝えています。

境内の見どころと宝物
広済寺の境内には、訪れる人々を魅了する見どころが数多く点在しています。
- 本尊: 方便法身尊影(御絵像)
- 本尊である方便法身尊影(御絵像)は、実如上人による裏書があり、その歴史的価値を示しています。
- 主要な寺宝
- 当寺院には、激動の時代を生き抜いた歴史の重みを伝える貴重な寺宝が伝えられています。
- 刀: 三代目看坊である祐盛が使用したと伝わる刀は、御山御坊陥落後の困難な時代に法灯を守り続けた、その歴史を物語る貴重な品です。
- 兜・面頬(めんぼお): 三代目看坊である祐盛が使用したと伝わる兜は、現在、石川県立歴史博物館に寄託されており、その歴史的価値が広く認められています。
- 当寺院には、激動の時代を生き抜いた歴史の重みを伝える貴重な寺宝が伝えられています。
これらの武具は、広済寺の歴史、特に加賀一向一揆の時代における重要な役割を今に伝える貴重な証です。
広済寺に伝わるこれら貴重な宝物や文化財の一部は、「文化財ギャラリー」でも高精細画像でご覧いただけます。
拝観案内・アクセス
広済寺へのご参拝に関する情報です。
- 宗派: 真宗大谷派
- 山号・寺号: 武佐山 広済寺 (通称: ムサ寺)
- 本尊: 方便法身尊影(木仏本尊)
拝観時間: 9:00~16:00 拝観料金: 無料
所在地: 〒920-0857 石川県金沢市扇町12-21
電話番号: 076-261-4609
公共交通機関:
- JR金沢駅より: バスで約11分、「出羽町」バス停下車、徒歩約10分。
お車でお越しの場合:
- 北陸自動車道金沢森本ICよりより約15分。
- 専用駐車場なし(お近くのコインパーキングをご利用ください)。